一頃パニック映画がブームになったことがあったが、そのひとつにマーク・ロブソン監督の『大地震』(Earthquake‐1974)というのがあった。
ロサンゼルス大地震を題材にしたパニック映画で、チャールトン・ヘストン、エヴァ・ガードナーらが出演していた。
この作品が蚤助にとって懐かしいのは、今から20年ほど前、妻子とともに訪れたマイアミのユニヴァーサル・スタジオに「大地震」と名付けられたアミューズメント施設があって、結構楽しんだ記憶があるからだ。
地震によるビルの崩壊や火災、洪水などが映画の特殊効果等の技術によってリアリティいっぱいに再現され、客が映画の登場人物と同様のパニック体験ができるというものだった。
また、やはりパニック映画に「大空港」シリーズがあって4作ほど作られたが、たまたまバート・ランカスターが主演した『大空港』が大ヒットしたため、二匹目、三匹目のドジョウを狙って続く作品が製作されたものであろう。
だが、シリーズものによくあるように、これも後続の作品ほど出来が悪くなっていった。
豪華キャストを揃え、パニックの設定や描写もそれなりに工夫がこらされているのに、全体としてチープな印象しか残らないのは、肝心の人間のドラマが薄っぺらだからである。
まことに残念なシリーズというべきであった(笑)。
ところで、『大地震』、大空港シリーズの3作目『エアポート'77/バミューダからの脱出』、4作目の『エアポート'80』に、モニカ・ルイスというちょっとジョーン・フォンテーンに感じが似た美人女優が出演していた。
彼女は歌も上手くて、何枚かアルバムを出しているが、“FOOLS RUSH IN”と題したアルバムがあるのだ(冒頭画像)。
録音は50年代の中頃であろうか。
昨今、ジャケ買い、すなわち、内容はともかくジャケットに惹かれてアルバムを買うということが巷で流行っているが、中古レコード・CDショップではわざわざ「ジャケ買い」のためのコーナーを設けているところもある。
店主も心得たもので、客の気を惹きそうなものをあれこれと取り揃えている。
「蚤助のジャケ買いというのはどうせヌードだろう」という声がどこからか聞こえてきそうだが、それは若いころのハナシであって、最近はもっと現実的なのである(笑)。
モニカ・ルイス嬢のこのアルバムのジャケットはグラフィック・デザイナーのバート・ゴールドブラットの手になるもので、ジャケットの左下に小さく彼の名前がクレジットされている。
なかなかいいジャケットでしょ?
元々10インチ盤で出たオリジナル・ジャケットを使用したCDなのだが、これとは別に同一内容でジャケット違いの“BUT BEAUTIFUL”と題されたCDも出ている。
彼女が歌う“FOOLS RUSH IN”は、50年代の典型的な白人女性シンガーのスタイルで、ジャック・ケリーのアレンジとアンサンブルを伴奏に個性的な歌を披露している。
ちなみに、こちらに出てくる写真がジャケット違いの“BUT BEAUTIFUL”である。
この頃活躍した多くの女性シンガーの中でも、特にGIに人気があった歌い手だそうで、なるほどドラマティックながら時には優しく包み込むような母性を感じさせるところがあり、兵隊たちの郷愁を誘う声だったのであろう。
ということで、だいぶ長いイントロだが、今回のお題は“FOOLS RUSH IN”という曲なのである。
前稿が“LUSH LIFE”と“LUSH”だったので、今回は“FOOLS RUSH IN”と“RUSH”で、ラッシュはラッシュでも“L”から“R”へと話題は連想ゲームのように移ったのだ。
さて、この曲、歌手上がりで、作詞のセンスを買われて作詞家に転身し、みごとに大家となったジョニー・マーサーが作詞したものである。
アメリカの主な作曲家のほとんどに詞を提供し、数々の名曲を生み出し、キャピトル・レコードの設立者の一人としても知られる。
そのマーサーが、リューブ・ブルーム(作曲)と組んで、1940年に発表した。
かつて、ファンから“ザ・ヴォイス”(THE VOICE)という愛称を献上されたフランク・シナトラが素晴らしいバラードのひとつとして例に挙げたことがあるナンバーだが、40年当時トミー・ドーシー楽団の専属シンガーであった若き日のシナトラ自身が歌って大ヒットさせた曲なので、持ち上げるのも当然といえば当然であった(笑)。
以後、シナトラにとっては大切なレパートリーとなって、何度か録音しているのだが、60年にネルソン・リドルのアレンジで歌ったものが、特に素晴らしく蚤助お気に入りである(こちら)。
![]()
(FRANK SINATRA/NICE 'N' EASY)
このアレンジはそのままカラオケとして発売されたことがあるそうで、そのカラオケで歌ってシナトラの気分になってみたいものだが、気分はシナトラでも上手に歌えるかどうかはまた別のハナシであることは「十分承知の介」である(笑)。
“RUSH”は、「急ぐ、せきたてる、突進、殺到、忙しさ、勢いよく流れる…」などという意味だが、“RUSH IN”だと「駆け込む、飛び込む」という意味であろうか。
“FOOLS”はもちろん「馬鹿、愚か者」のことである。
Fools rush in where angels fear to tread
And so I come to you my love, my heart above my head…
愚か者は飛び込む 天使が踏み込むのを恐れるところへ
そして私も来てしまった あなたのもとへ
私の心は頭の上にあるようだ
危険は承知しているけれど でもチャンスがあるならかまわない
愚か者は駆け込んでいく 賢者が決して行かないところへ
でも賢者は決して恋をしたりしない ならばそんな人たちに何が分かるというのか
あなたに出会って私の人生は始まった だから心を開いてほしい
この愚か者のために…
“FOOLS”が“RUSH IN”するのは「恋」であって、恋をするのは愚か者だと言っているのだが、「私」は喜んで愚か者になろうというのである。
恋する男を愚か者に、それに賢者を対比させたちょっと凝った詞も、甘く悲しいムードをたたえたメロディも実に良い。
ここにいる恋する者を受け入れてほしい…といささかへりくだった表現の中に、恋はすべてのものに盲目となることを証明したような歌だ。
『恋は愚かというけれど』というなかなか秀逸な邦題がつけられている。
実はこの曲の歌詞の出だしがそのまま格言になっているのだ。
“FOOLS RUSH IN WHERE ANGELS FEAR TO TREAD”
「天使も恐れるところへ愚者は踏み込む」、すなわち「愚者はこわいものを知らない」という意味で、日本のことわざで言えば「盲蛇におじず」と、高校時代からお世話になってきたおなじみ研究社の新英和中辞典の“Angel”のところに出ている。
愚かな者は何が恐ろしいか、恐ろしくないかを知らないので、どんな危険なことでも平気でやってしまう、無鉄砲なことがある、というわけだ。
リッキー・ネルソンが古いスタンダード曲を取り上げた例はそんなに多くないが、だいぶ大人っぽくなった63年にこの“FOOLS RUSH IN”をシングル盤として発売し、リバイバル・ヒットさせている。
名前もリッキーからリックに変え、エコーをかけた多重録音でアップ・テンポで歌った(こちら)。
また、“キング”・エルヴィス・プレスリーも歌っているが、リック・ネルソンよりも少し重厚で渋く、はるかに上手い(こちら)。
喋らなきゃバカもしばらくわからない(蚤助)
ロサンゼルス大地震を題材にしたパニック映画で、チャールトン・ヘストン、エヴァ・ガードナーらが出演していた。
この作品が蚤助にとって懐かしいのは、今から20年ほど前、妻子とともに訪れたマイアミのユニヴァーサル・スタジオに「大地震」と名付けられたアミューズメント施設があって、結構楽しんだ記憶があるからだ。
地震によるビルの崩壊や火災、洪水などが映画の特殊効果等の技術によってリアリティいっぱいに再現され、客が映画の登場人物と同様のパニック体験ができるというものだった。
また、やはりパニック映画に「大空港」シリーズがあって4作ほど作られたが、たまたまバート・ランカスターが主演した『大空港』が大ヒットしたため、二匹目、三匹目のドジョウを狙って続く作品が製作されたものであろう。
だが、シリーズものによくあるように、これも後続の作品ほど出来が悪くなっていった。
豪華キャストを揃え、パニックの設定や描写もそれなりに工夫がこらされているのに、全体としてチープな印象しか残らないのは、肝心の人間のドラマが薄っぺらだからである。
まことに残念なシリーズというべきであった(笑)。
ところで、『大地震』、大空港シリーズの3作目『エアポート'77/バミューダからの脱出』、4作目の『エアポート'80』に、モニカ・ルイスというちょっとジョーン・フォンテーンに感じが似た美人女優が出演していた。
彼女は歌も上手くて、何枚かアルバムを出しているが、“FOOLS RUSH IN”と題したアルバムがあるのだ(冒頭画像)。
録音は50年代の中頃であろうか。
昨今、ジャケ買い、すなわち、内容はともかくジャケットに惹かれてアルバムを買うということが巷で流行っているが、中古レコード・CDショップではわざわざ「ジャケ買い」のためのコーナーを設けているところもある。
店主も心得たもので、客の気を惹きそうなものをあれこれと取り揃えている。
「蚤助のジャケ買いというのはどうせヌードだろう」という声がどこからか聞こえてきそうだが、それは若いころのハナシであって、最近はもっと現実的なのである(笑)。
モニカ・ルイス嬢のこのアルバムのジャケットはグラフィック・デザイナーのバート・ゴールドブラットの手になるもので、ジャケットの左下に小さく彼の名前がクレジットされている。
なかなかいいジャケットでしょ?
元々10インチ盤で出たオリジナル・ジャケットを使用したCDなのだが、これとは別に同一内容でジャケット違いの“BUT BEAUTIFUL”と題されたCDも出ている。
彼女が歌う“FOOLS RUSH IN”は、50年代の典型的な白人女性シンガーのスタイルで、ジャック・ケリーのアレンジとアンサンブルを伴奏に個性的な歌を披露している。
ちなみに、こちらに出てくる写真がジャケット違いの“BUT BEAUTIFUL”である。
この頃活躍した多くの女性シンガーの中でも、特にGIに人気があった歌い手だそうで、なるほどドラマティックながら時には優しく包み込むような母性を感じさせるところがあり、兵隊たちの郷愁を誘う声だったのであろう。
ということで、だいぶ長いイントロだが、今回のお題は“FOOLS RUSH IN”という曲なのである。
前稿が“LUSH LIFE”と“LUSH”だったので、今回は“FOOLS RUSH IN”と“RUSH”で、ラッシュはラッシュでも“L”から“R”へと話題は連想ゲームのように移ったのだ。
さて、この曲、歌手上がりで、作詞のセンスを買われて作詞家に転身し、みごとに大家となったジョニー・マーサーが作詞したものである。
アメリカの主な作曲家のほとんどに詞を提供し、数々の名曲を生み出し、キャピトル・レコードの設立者の一人としても知られる。
そのマーサーが、リューブ・ブルーム(作曲)と組んで、1940年に発表した。
かつて、ファンから“ザ・ヴォイス”(THE VOICE)という愛称を献上されたフランク・シナトラが素晴らしいバラードのひとつとして例に挙げたことがあるナンバーだが、40年当時トミー・ドーシー楽団の専属シンガーであった若き日のシナトラ自身が歌って大ヒットさせた曲なので、持ち上げるのも当然といえば当然であった(笑)。
以後、シナトラにとっては大切なレパートリーとなって、何度か録音しているのだが、60年にネルソン・リドルのアレンジで歌ったものが、特に素晴らしく蚤助お気に入りである(こちら)。
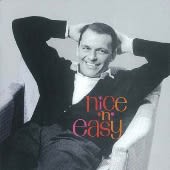
(FRANK SINATRA/NICE 'N' EASY)
このアレンジはそのままカラオケとして発売されたことがあるそうで、そのカラオケで歌ってシナトラの気分になってみたいものだが、気分はシナトラでも上手に歌えるかどうかはまた別のハナシであることは「十分承知の介」である(笑)。
“RUSH”は、「急ぐ、せきたてる、突進、殺到、忙しさ、勢いよく流れる…」などという意味だが、“RUSH IN”だと「駆け込む、飛び込む」という意味であろうか。
“FOOLS”はもちろん「馬鹿、愚か者」のことである。
Fools rush in where angels fear to tread
And so I come to you my love, my heart above my head…
愚か者は飛び込む 天使が踏み込むのを恐れるところへ
そして私も来てしまった あなたのもとへ
私の心は頭の上にあるようだ
危険は承知しているけれど でもチャンスがあるならかまわない
愚か者は駆け込んでいく 賢者が決して行かないところへ
でも賢者は決して恋をしたりしない ならばそんな人たちに何が分かるというのか
あなたに出会って私の人生は始まった だから心を開いてほしい
この愚か者のために…
“FOOLS”が“RUSH IN”するのは「恋」であって、恋をするのは愚か者だと言っているのだが、「私」は喜んで愚か者になろうというのである。
恋する男を愚か者に、それに賢者を対比させたちょっと凝った詞も、甘く悲しいムードをたたえたメロディも実に良い。
ここにいる恋する者を受け入れてほしい…といささかへりくだった表現の中に、恋はすべてのものに盲目となることを証明したような歌だ。
『恋は愚かというけれど』というなかなか秀逸な邦題がつけられている。
実はこの曲の歌詞の出だしがそのまま格言になっているのだ。
“FOOLS RUSH IN WHERE ANGELS FEAR TO TREAD”
「天使も恐れるところへ愚者は踏み込む」、すなわち「愚者はこわいものを知らない」という意味で、日本のことわざで言えば「盲蛇におじず」と、高校時代からお世話になってきたおなじみ研究社の新英和中辞典の“Angel”のところに出ている。
愚かな者は何が恐ろしいか、恐ろしくないかを知らないので、どんな危険なことでも平気でやってしまう、無鉄砲なことがある、というわけだ。
リッキー・ネルソンが古いスタンダード曲を取り上げた例はそんなに多くないが、だいぶ大人っぽくなった63年にこの“FOOLS RUSH IN”をシングル盤として発売し、リバイバル・ヒットさせている。
名前もリッキーからリックに変え、エコーをかけた多重録音でアップ・テンポで歌った(こちら)。
また、“キング”・エルヴィス・プレスリーも歌っているが、リック・ネルソンよりも少し重厚で渋く、はるかに上手い(こちら)。
喋らなきゃバカもしばらくわからない(蚤助)