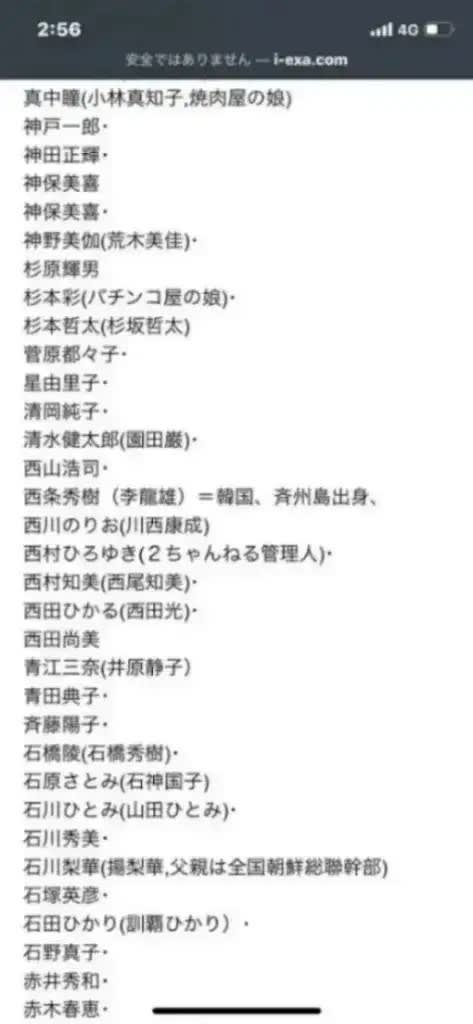“ジョン・ヘイリー・シムズ”は、かつて“四人兄弟”の一人であった。
♪
こう書くと「何のこっちゃ?」と思う人もいるだろう。
ジョン・ヘイリー・シムズとは、サックス奏者ズート・シムズ(1925‐1985)の本名である。
“ズート”(Zoot)というのはかなり珍しいニックネームだが、その由来については、彼がいつもダブダブの服装をしていたからだとか、いつも酔っぱらって服装がだらしなかったからだとか、いろいろな説があるようだ。
辞書にも載っている“Zoot Suit”といえば、1940年代にアメリカで流行ったメンズ・ファッションで、肩幅が広く長めの上着とすそが細くなったダブダブのズボンからなるスーツのことを指すが、私なりに考えれば、彼が肩幅が広いいかり肩だったことからきているような気がする。
どなたか“ズート”という命名の真相をご存じの方がいたらご教示いただきたいものである。
ニックネームの由来はともかくとして、彼は16才のときにプロ入りして数々のバンドで活動をしたが、1947年、ウディ・ハーマン楽団のセカンド・ハードに加わると、一躍スター・プレイヤーとなった。
四人兄弟というのは、このウディ・ハーマン・セカンド・ハードの名演奏“FOUR BROTHERS”で組んだサックス・セクション4人組のことを指している。
それまでのビッグ・バンドのサックス・パートがアルトがリードするというスタイルだったのに対し、この曲ではテナーのリードによる“ソリ”と4人のサックス奏者によるソロ・パートからなる画期的なものであった。
このときのスタン・ゲッツ、ズート・シムズ、ハービー・スチュワード、サージ・チャロフが四人兄弟なのだった。
シムズはスタン・ゲッツとともにこの演奏で名を挙げるのである。
♪ ♪
前稿で、ケニー・バレルについて「駄作がない」と書いたが、シムズに関しても全く同じことが言える。
彼は、リーダー吹き込みに加え、サイドマンとしても実に多くのセッションに参加している。
アルファベットの最初の“A”と最後の“Z”の白人テナー奏者二人の組み合わせで人気が高かったアル・コーンとのコンビ作品(AL & ZOOT)のほか、コンボからオーケストラ、さらに歌伴まで加えると残されたレコーディングは膨大なものである。
これだけ多くの録音を残しながらも、一つとして凡打がないというのは、彼の高い音楽性を示すものである。
![]()
四人兄弟のもう一人のスター、スタン・ゲッツとは同年代で、同じレスター・ヤング派の一員としてプレイ・スタイルも似通っているのだが、ゲッツと比べると地味な存在であった。
それでも、時流に媚びることなく自分自身を守り通しただけあって、年を経るごとに大家の風格が備わるようになっていった。
彼の演奏は、「職人芸」と言う言葉がぴったりくる。
手にする楽器のコントロールやテクニックは熟練の極みだし、それでいてハッタリやケレン味がない、人間味あふれた表現力が彼の最大の魅力であった。
歴代の天才、巨匠、名人たちの中には、晩年期に至って、ひどく凋落した演奏しか披露できなかった人も多いが、シムズの場合は最後までその魅力を失わず、名手のままその風格を保ち続けた人であった。
♪ ♪ ♪
彼の個性が最も効果的に発揮され、即興演奏家としての本領を発揮するのが、ワン・ホーン・カルテットであった。
晩年にいたってもワン・ホーンの快演、好演を連発したシムズだが、今回挙げたのは“DOWN HOME”(1960)というタイトルの一枚である。
![]()
1. Jive At Five
2. Doggin' Around
3. Avalon
4. I Cried For You
5. Bill Bailey
6. Good Night Sweetheart
7. There'll Be Some Changes Made
8. I've Heard That Blues Before
9. There'll Be Some Changes Made (Alt.)
10. Jive At Five (Alt.)
11. Doggin' Around (Alt.)
12. Avalon (Alt.)
13. Good Night Sweetheart (Alt.)
14. Bill Bailey (Alt.)
シムズは、バラードでもアップテンポでも上手いが、最も得意としたのがミディアム・テンポで、ステーキの焼き加減ではないが「ミディアム」が一番美味しい。
このアルバムではミディアム・ナンバーを中心にしているだけあって、その本領を発揮していることに加え、リズム・セクションに第一級の人材が配されていることが大きな魅力である。
実力派で強力なジョージ・タッカーのベースをバックに、チャールズ・ミンガス・グループのドラマー、ダニー・リッチモンドが刺激的に煽り立てるドラムスに乗って、多芸多才なピアノの名手デイヴ・マッケンナが素晴らしい乗りで迫ると、シムズはハードなドライヴ感でダイナミズムにあふれた演奏を展開する。
快適で、理想的ともいえるスウィング感である。
この感覚は、黒人ジャズの粘っこい乗りとは異なるが、何だか生理的な快感に訴えてくるものがある。
彼は、常に「前衛」という言葉とは無縁の地点にいたが、その生涯を通じて、よく歌い、よくスウィングする第一級のソロイストであった。
円熟度を加えた晩年の作品もすばらしいが、このアルバムのように、重量感にあふれていながらも、タイトル通り“DOWN HOME”な(くつろぎに満ちた)演奏はやはり最高である。
レコード・CD棚をひっくり返してみたら、ズート・シムズは、いつの間にか、ソニー・ロリンズ、スタン・ゲッツ、ジョン・コルトレーンに次いで、我がコレクションの中で大きな分量を占めるサックス奏者になっていたのだった。
Mr. Sims, Medium, Please!
リラックスしなきゃならぬと力む癖 (蚤助)
♪
こう書くと「何のこっちゃ?」と思う人もいるだろう。
ジョン・ヘイリー・シムズとは、サックス奏者ズート・シムズ(1925‐1985)の本名である。
“ズート”(Zoot)というのはかなり珍しいニックネームだが、その由来については、彼がいつもダブダブの服装をしていたからだとか、いつも酔っぱらって服装がだらしなかったからだとか、いろいろな説があるようだ。
辞書にも載っている“Zoot Suit”といえば、1940年代にアメリカで流行ったメンズ・ファッションで、肩幅が広く長めの上着とすそが細くなったダブダブのズボンからなるスーツのことを指すが、私なりに考えれば、彼が肩幅が広いいかり肩だったことからきているような気がする。
どなたか“ズート”という命名の真相をご存じの方がいたらご教示いただきたいものである。
ニックネームの由来はともかくとして、彼は16才のときにプロ入りして数々のバンドで活動をしたが、1947年、ウディ・ハーマン楽団のセカンド・ハードに加わると、一躍スター・プレイヤーとなった。
四人兄弟というのは、このウディ・ハーマン・セカンド・ハードの名演奏“FOUR BROTHERS”で組んだサックス・セクション4人組のことを指している。
それまでのビッグ・バンドのサックス・パートがアルトがリードするというスタイルだったのに対し、この曲ではテナーのリードによる“ソリ”と4人のサックス奏者によるソロ・パートからなる画期的なものであった。
このときのスタン・ゲッツ、ズート・シムズ、ハービー・スチュワード、サージ・チャロフが四人兄弟なのだった。
シムズはスタン・ゲッツとともにこの演奏で名を挙げるのである。
♪ ♪
前稿で、ケニー・バレルについて「駄作がない」と書いたが、シムズに関しても全く同じことが言える。
彼は、リーダー吹き込みに加え、サイドマンとしても実に多くのセッションに参加している。
アルファベットの最初の“A”と最後の“Z”の白人テナー奏者二人の組み合わせで人気が高かったアル・コーンとのコンビ作品(AL & ZOOT)のほか、コンボからオーケストラ、さらに歌伴まで加えると残されたレコーディングは膨大なものである。
これだけ多くの録音を残しながらも、一つとして凡打がないというのは、彼の高い音楽性を示すものである。

四人兄弟のもう一人のスター、スタン・ゲッツとは同年代で、同じレスター・ヤング派の一員としてプレイ・スタイルも似通っているのだが、ゲッツと比べると地味な存在であった。
それでも、時流に媚びることなく自分自身を守り通しただけあって、年を経るごとに大家の風格が備わるようになっていった。
彼の演奏は、「職人芸」と言う言葉がぴったりくる。
手にする楽器のコントロールやテクニックは熟練の極みだし、それでいてハッタリやケレン味がない、人間味あふれた表現力が彼の最大の魅力であった。
歴代の天才、巨匠、名人たちの中には、晩年期に至って、ひどく凋落した演奏しか披露できなかった人も多いが、シムズの場合は最後までその魅力を失わず、名手のままその風格を保ち続けた人であった。
♪ ♪ ♪
彼の個性が最も効果的に発揮され、即興演奏家としての本領を発揮するのが、ワン・ホーン・カルテットであった。
晩年にいたってもワン・ホーンの快演、好演を連発したシムズだが、今回挙げたのは“DOWN HOME”(1960)というタイトルの一枚である。

1. Jive At Five
2. Doggin' Around
3. Avalon
4. I Cried For You
5. Bill Bailey
6. Good Night Sweetheart
7. There'll Be Some Changes Made
8. I've Heard That Blues Before
9. There'll Be Some Changes Made (Alt.)
10. Jive At Five (Alt.)
11. Doggin' Around (Alt.)
12. Avalon (Alt.)
13. Good Night Sweetheart (Alt.)
14. Bill Bailey (Alt.)
シムズは、バラードでもアップテンポでも上手いが、最も得意としたのがミディアム・テンポで、ステーキの焼き加減ではないが「ミディアム」が一番美味しい。
このアルバムではミディアム・ナンバーを中心にしているだけあって、その本領を発揮していることに加え、リズム・セクションに第一級の人材が配されていることが大きな魅力である。
実力派で強力なジョージ・タッカーのベースをバックに、チャールズ・ミンガス・グループのドラマー、ダニー・リッチモンドが刺激的に煽り立てるドラムスに乗って、多芸多才なピアノの名手デイヴ・マッケンナが素晴らしい乗りで迫ると、シムズはハードなドライヴ感でダイナミズムにあふれた演奏を展開する。
快適で、理想的ともいえるスウィング感である。
この感覚は、黒人ジャズの粘っこい乗りとは異なるが、何だか生理的な快感に訴えてくるものがある。
彼は、常に「前衛」という言葉とは無縁の地点にいたが、その生涯を通じて、よく歌い、よくスウィングする第一級のソロイストであった。
円熟度を加えた晩年の作品もすばらしいが、このアルバムのように、重量感にあふれていながらも、タイトル通り“DOWN HOME”な(くつろぎに満ちた)演奏はやはり最高である。
レコード・CD棚をひっくり返してみたら、ズート・シムズは、いつの間にか、ソニー・ロリンズ、スタン・ゲッツ、ジョン・コルトレーンに次いで、我がコレクションの中で大きな分量を占めるサックス奏者になっていたのだった。
Mr. Sims, Medium, Please!
リラックスしなきゃならぬと力む癖 (蚤助)